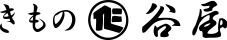京都西陣は、高級な先染めの絹織物産地として有名です。
礼装用の袋帯を中心に、様々な伝統技法による織物が生産されています。
今回は、西陣織の機屋(はたや)・田村屋が手がけるブランド『螢庵』の帯と着物についてご紹介します。
職人技が受け継がれる「京都・西陣織」

最高級の織物として
西陣織は、京都の西陣で生産される「先染め」の紋織物です。
友禅染めに代表されるような「後染め」は、織り上がった生地の上に後から柄を描きます。
これに対し「先染め」の織物では、様々な色糸や金糸・銀糸を使って、柄を織り出しています。
後染めの製品は「染め」、先染めの製品は「織り」とも呼ばれます。
着物の場合は、「染め」の製品の方が、紬など「織り」の製品よりも格式が高いとされており、振袖・留袖・訪問着などの礼装は「染め」の着物です。
一方、帯の場合には、「織り」の製品の方が「染め」の製品よりも格上とされます。
京都・西陣織は、振袖・留袖・訪問着など、礼装に合わせる最高級の帯で有名です。
西陣織の特徴とは?
西陣織の特徴の一つが「多品種少量生産」です。
手間と時間のかかる高級織物ですので、大量生産されることはなく、一つ一つの製品に希少価値が生まれます。
品格ある西陣織の袋帯は、親から子へ世代を超えて受け継ぐことができる逸品ばかりです。
また、京都の着物・帯の特徴として、職人集団による「分業制」もよく知られています。
東京や金沢など、他の主な着物産地では、一つの工房内で完結する「一貫生産」が主流です。
京都では、伝統技法のそれぞれの工程を専門の職人が担当し、分業・協業で製品を完成させる生産方式がとられています。
「染めと織り」の長い歴史を持つ京都でしか実現できない生産方式とも言えます。
様々な伝統技法を受け継ぐ職人が集まる京都では、職人技を結集した新しい「ものづくり」への挑戦も常に行われています。
伝統と革新が交差する「京都・西陣」は、これからも日本の織物産地の「トップランナー」であり続けることでしょう。
田村屋『螢庵』の帯

『螢庵』は、京都西陣織の機屋・田村屋の人気ブランドです。
創業者である先代の田村螢成(けいせい)氏が京都美山町に結んだ庵の名前が由来となっています。
現社長の田村隆久氏は、同志社大学ビジネススクール出身の経営者でもあります。
機屋として伝統技術を継承するだけでなく、伝統産業の成長・発展にも手腕を発揮しています。

経錦(たてにしき)
『螢庵』の帯や着物に使われる代表的な技法の一つです。
経糸(たていと)で地と文様を織り出す「経錦」は、「錦」織りの中でも最古の技法とされています。
経錦では、緯錦(よこにしき)のように裏側に糸が渡らないので、表側だけでなく裏側も滑らかで美しい仕上がりになります。
この特徴を生かし、『螢庵』の帯には両面使用(リバーシブル)のデザインが数多くあります。
高級な袋帯が両面使用できたら、とってもお得で便利ですよね。
経錦の帯は、文様のための緯糸が無い分、軽くて締めやすいというメリットもあります。
本袋帯(ほんふくろおび)
現代の袋帯は、大半が表地と裏地を縫い合わせて袋状に仕立てています。
これに対して、「本袋帯」は表と裏が一枚の織物として筒状に織り上げられています。
「裏返し」の状態で織られるため、織り上がって「表返す」までは、織り手でも模様を見ることができません。そのため、高い技術が必要とされます。
ちなみに、田村屋さんのインスタグラムでは、織り上がった美しい本袋帯を「裏返す(表返す)」様子が動画で公開されていますので、ぜひチェックしてみてください。
本袋帯には両端の縫い代が無いため、型崩れしにくく、締め心地が良いという特長があります。
『螢庵』の本袋帯は、両面使える(リバーシブル)全通柄で織られています。
全通柄は、帯地全体に柄が織り出されている帯のことで、柄が多い分、高級なつくりです。無地の部分を気にせずに着付けることができるので、体型に関係なく使用できるという利点があります。
「箔(はく)」の帯

「箔」とは、金・銀・プラチナなどの金属を薄くシート状にした物のことを言います。
帯に使われる場合には、和紙に漆を塗り「箔」を貼り付けて裁断したものを帯に織り込みます。
・引箔(ひきばく)
箔に柄を描き糸状に細かく裁断してから帯に織り込みます。これにより、描いた柄が織物に再現されます。
・古箔(こばく)
文化財を修復する目的で「経年変化」の風合いを再現した箔です。
・揉み箔(もみはく)
箔を揉みこんで「シワ」をつけたものです。手作業でつけた自然な「揉みじわ」が、独特な風合いを醸し出します。
色無地着物「待庵」
西陣織というと帯のイメージが強いですが、『螢庵』ではオリジナルの着物も製作しています。
京都の仏教寺院妙喜庵の中にある「待庵(たいあん)」は、千利休が建てたとされる日本最古の茶室です。
この茶室の土壁をモチーフとして製作されたのが、『螢庵』の色無地着物「待庵」です。
お茶席の着物にも最適な一品です。
『螢庵』の着物と帯を谷屋で
千葉県香取市の谷屋呉服店では、日本各地の名品を取り寄せた展示会を定期的に開催しています。
今後、京都西陣織『螢庵』の着物や帯を一堂に会する展示会も開催予定となっております。 流通量が少ない貴重な逸品をご覧いただけるチャンスですので、その折はぜひお立ち寄りくださいませ。